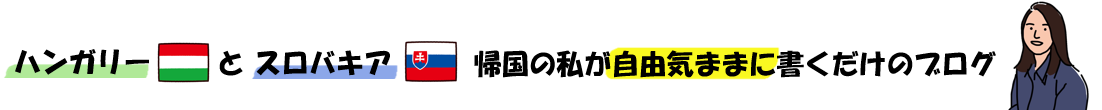このブログを書いていくにあたって、「帰国子女」の定義は重要なポイントになります。
必ずしも「英語が話せる人=帰国子女」ではないからです。
定義を考える
まずはネット上における「帰国子女」の定義を調べてみましょう。
親の仕事の都合などで長年海外で過ごして帰国した子供。
帰国子女(きこくしじょ)とは? 意味・読み方・使い方をわかりやすく解説 – goo国語辞書
「帰国児童生徒」とは、海外勤務者等の子女で、引き続き1年を越える期間海外に在留し、各年度間帰国した児童生徒を言う。
文部科学省-海外で学ぶ日本の子どもたち-
「帰国児童・生徒」とは、海外勤務者等の児童・生徒で、引続き1年を超える期間海外に在留し、前年4月1日から翌年3月31日までの間に帰国した児童・生徒をいいます。
統計局ホームページ/統計FAQ 22A-Q05 帰国児童・生徒数及び外国人児童・生徒数
ここでハッとしました。

もしかして、学生期間を終えた大人になってからの海外滞在は「帰国子女」にならないのでは?
確かに私は小学校1年生~中学校3年生をヨーロッパで過ごしたことで、考え方や性格など、すべてに大きな変化がありました。
一方、当時30~40代だった両親を見てみると、私ほど大きな変化はありません。
もちろん国際的な人材になったことで、視野が広がるなどの違いは見られますが、子供の頃に過ごした人と比べるとインパクトは小さいです。
例えば、両親が仕事の話でぷんすか怒った内容を共有されると、私は必ず「でも結果がすべてだよね?」や「自動車事故とは違って、人間関係において原因が片方のみに偏ることはありえない。」と内心、外資系志向強めのコメントが出ます。

俺の方が地位が上だし、経験に基づいた結論なんだからお前は従ぇ~
いやいや。人間一人の経験なんてたかが知れてますやん。
老若男女問わず、互いに尊重しあって仕事をするべきだと個人的には思います。
そんな上下関係がある時点で、人間関係が成り立つわけがない、と思うのです。
こんな風に親子でも理解し合えなくなるくらい、小さいころからの海外経験は大きいと私は思います。
でもこれはとても良い傾向だと思います。
なぜなら教育において、子供の成長を一番に止めてしまうの”親”だからです。
帰国子女にもタイプがある?
私の中では、帰国子女(以下、帰国という)には2つのタイプがあります。
「もろ帰国」タイプと「隠れ帰国」タイプです。
このブログにおいて、
「もろ帰国」とは、
日本語(母国語)に加え、英語あるいは他の言語をネイティブレベルで話せる人を指します。
「隠れ帰国」とは、
長期間海外に滞在していたが、日本人学校など日本とさほど変わらない環境にいたため、他言語を話せない人 or そもそも小さい頃過ぎて記憶にない人を指します。

私は”もろ帰国”タイプです。日本語、英語はネイティブレベル。
加えて、ドイツ語もビジネスレベルです。
”通う学校”で人生が変わる?
海外生活で子供を学校に通わせる場合、大きく分けて3つの選択肢があります。
- 日本人学校
- 現地校
- インターナショナル学校(通称:インター校)
私はすべてのタイプの学校を経験しました。結構珍しいケースです。
よって、超個人的経験に基づいて、それぞれの主なメリット・デメリットを以下にまとめます。
日本人学校の場合
【メリット】
- 日本と基本的に変わらない教育を受けるため、本帰国した際スムーズに馴染める。
- 母国語がしっかり身につくため、社会人になっても難なく一人で生きていけるだろう。
- 滞在期間が短い場合、子供に環境変化による大きなストレスを与えずに済む。
- 日本人の知り合いが増えるため、現地のノウハウなど困ったときに助け合える。
【デメリット】
- 英語が身につかない。How are you? I’m fine thank you.を多用するくらい普通。
- 日本人に囲まれるため、国際的な人材としてもあまり期待できない。
- 日本の典型的な受験戦争に普通に巻き込まれる。
- 帰国だということをカミングアウトしづらい。もはや隠す人多い。
※英語圏の場合は日ごろから英語を耳にする機会が多いため、母国語とのバランスがとれるかもしれない。
現地校の場合
【メリット】
- 英語圏外の場合、英語以外の言語を使いこなせるくらいまでになる可能性あり。
- 現地人の知り合いが増え、医療機関など困ったときにかなり心強い。
- 本帰国した際に「現地校通い」はかなりパワーワード。勝ち組。
- 日本人学校やインター校と比べて、コスパが良い。
【デメリット】
- 小学校低学年であれば問題ないが、徐々に人種差別が目立ってくる。
*私は中学からだったので、かなりひどい目に逢いました… - 日本の公立学校のようなものなので、現地の民度を直に受ける。
- 現地人の習慣が良くも悪くも身につく。
大人になってタトゥーやたばこ、ギャンブルなどに抵抗がなくなる可能性あり。 - 教育方法に偏りが出る。
*例えばスロバキアの現地校は必須科目として英語ではなく、同じスラブ系民族としてロシア語を勉強させられます。
インターナショナル学校(インター校)の場合
英語圏外のインター校には「アメリカン系」と「ブリティッシュ系」があります。
どちらも個性を大事にする教育方針に変わりないですが、アメリカンは比較的自由な印象があります。ブリティッシュはハリーポ〇ターみたいな制服が多く、規則も若干厳しめ、学費も高めなど多少の違いはあります。
【メリット】
- 気が付いたら英語が母国語のように身についている。
- 必修科目で他の言語もある程度のレベルまで話せるようになる。
*私の場合、ハンガリーの頃はハンガリー語を選択。
スロバキアの頃は小学5年生の時点でフランス語を選択し、小学6年生以降はフランス語とドイツ語、両方が必修でした。 - 国籍が違う同士で毎日過ごすので、言うまでもなく国際的な人材になる。
- 個人のパフォーマンスが爆上がりする。人生勝ったようなもん。
*プレゼン、コミュニケーション能力、教養、考える力など。現代の日本人が持つ悩みはすでにこの時点で解決済み。
【デメリット】
- とにかく学費が高い。
- 学校数が少ないため、選択肢も少ない。
- 日本語と英語が中途半端になる可能性あり。(現地校も同様)
- 両親が英語を話せないと学校との連絡などで困る。(現地校も同様)
まとめ
<ポイント>
- 帰国子女にもいくつか種類がある。
- 通う学校によって得られるものがかなり変わってくる。
以上が帰国子女の定義に関する記事でした。
それぞれの学校での経験談はまた別の記事でまとめます。